『崩れ』を折る
比喩や寓意ではなく、地質学的な「崩れ」を直視する視線を描く。山って崩れるんだよな。
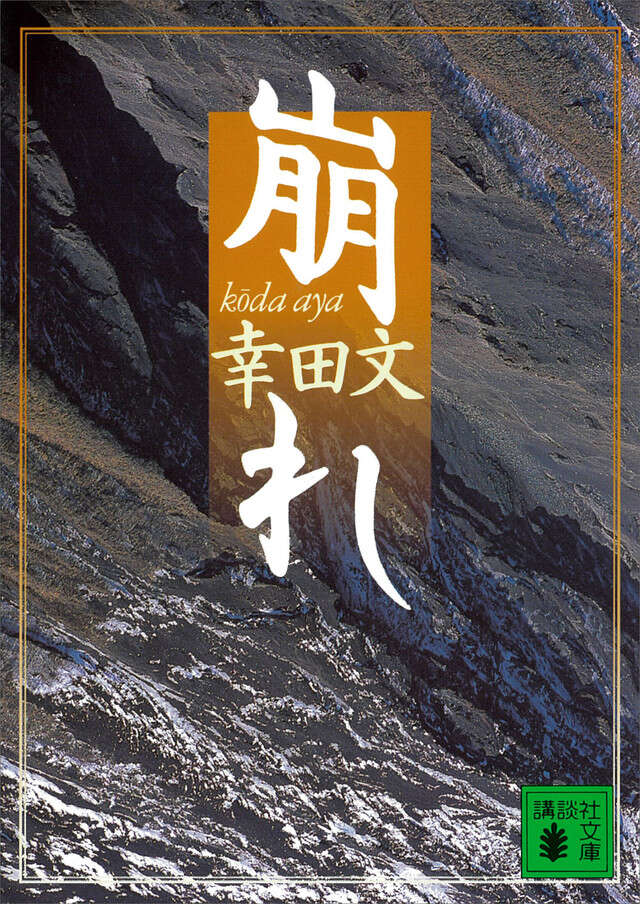
崩れ
講談社文庫
年に一度か二度、私は山に登る。最近では、燕岳から大天岳へ縦走したり、尾瀬の燧ヶ岳や富士山に足を運んだりした。眼前に開ける山の姿は、いつも堂々として、ただそこに「在る」ものとしか思っていなかった。
けれども、藤岡換太郎『山はどうしてできるのか―ダイナミックな地球科学入門(ブルーバックス)』(https://amzn.asia/d/aaMeInC)を読んでから、その見方も少し変わった。
山はどのように生まれるのか。プレートやマグマの発見以前に、人々はそれをどのように説明してきたのか。あたりまえのように「そこにある」山にも、数多の仮説と探究の歴史が潜んでいる。その壮大な試行錯誤に触れ、私は山の成り立ちに強く惹かれるようになった。
だが一方で、「山がいかに崩れるか」については、これまでほとんど思いを寄せてこなかったのである。そうした折に出会ったのが、幸田文の『崩れ』であった。
本の感想
そこに描かれるのは、比喩や寓意ではなく、まさに地質学的な「崩れ」を直視する視線である。七十を過ぎてなお全国の現場を訪ね歩き、土砂の裂け目に身を寄せる。山を崇めるのでもなく、ただ「崩れる」という現象を凝視することで、人間の営みそのものの脆さが照らし出される。
